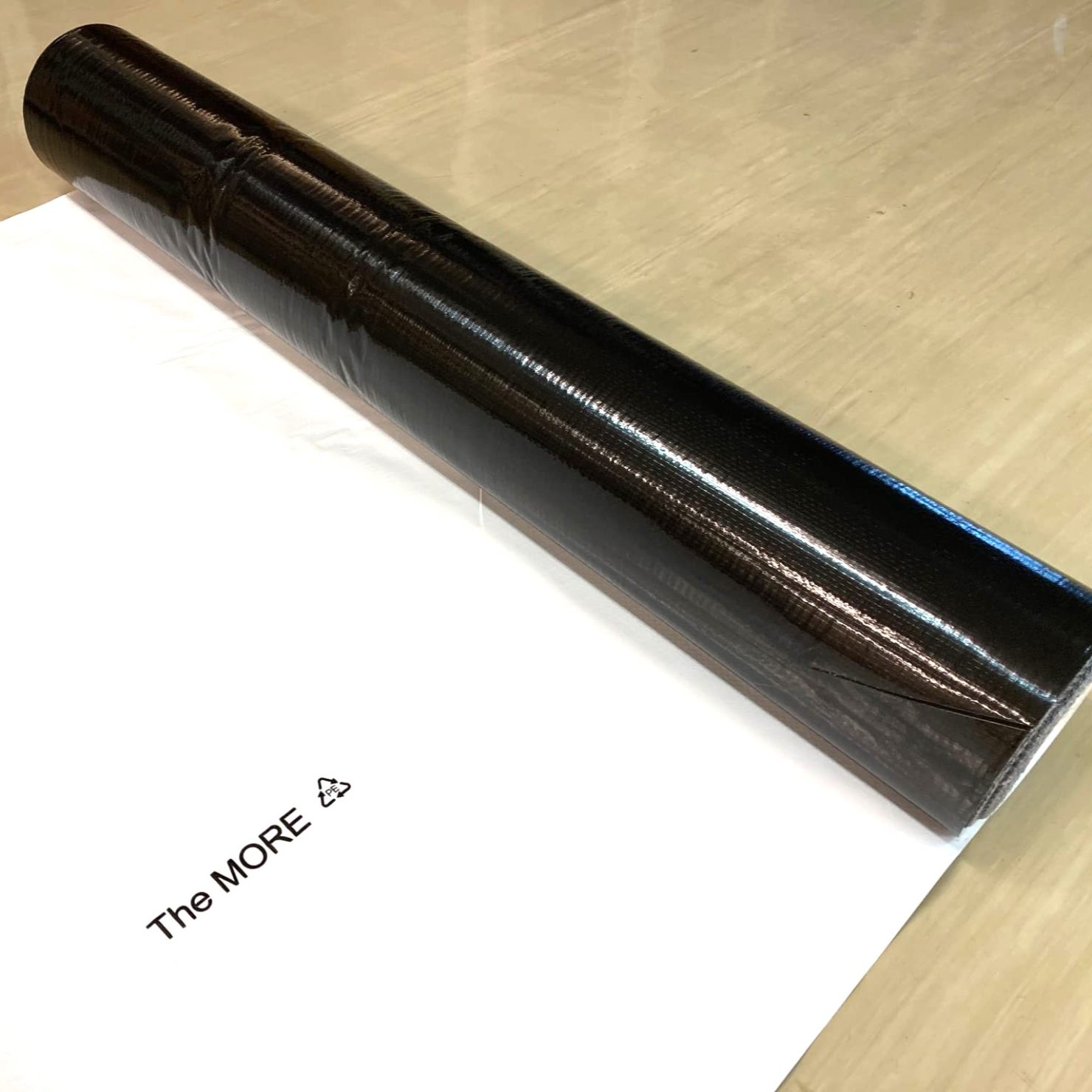トマト栽培ではこれらの病害虫被害に加えて数多くの「生理障害」が認められています。これらの生理障害のなかには日照不足に起因したものもあるため、日照対策がトマトの栽培においてとても大事なポイントとなっています。
今回のコラムは、トマト栽培における日照不足に焦点をあてて、その症状と対策を紹介したいと思います。

トマト栽培と日照の関係
トマトを栽培するには「日照」が不可欠です。
トマトの光合成特性からいえば、トマトの光飽和点*は70キロルクスといわれておりサトイモやスイカより低く、キュウリ、メロン、ブドウなどより高いとされています。しかし、トマトの光補償点**は他の農作物と比較してとくべつ高くはなく1.5キロルクスといわれています。トマトにおける光飽和点と光補償点の数値を読み解くと、弱い光でも生育が可能だが光飽和点が高いため、日照の強さによって生長速度にバラツキがあると考えられます。このことは果実品質に影響が及びやすいということであり、日照不足によって引き起こされる生理障害がトマト果実に悪影響を与える一因となっています。
トマトの花芽は本葉3枚おきに分化します。品種、株の生育状態(樹勢)、肥料の多少にもよりますが、本葉は主茎や果房に対して非常に葉面積が大きく、これはトマトが光合成を行うため光を求めて形態的に進化してきた(或いは改良)特徴であり、それだけ多くの日照を求めているからです。しかし、この大きな葉はお互いが重なり合うことで光合成を不効率にしています。実際に、ガラス温室で栽培されたトマト群落では好適な日照量を確保できず整枝方法に工夫が必要とされています。このようなトマト葉の繁茂に起因した日照不足に対しては、古くなった下葉を除去することや補光ライトで補助的に光合成を促すことで対策が行われています。
*光飽和点:光強度において、それ以上強い光をあてても光合成速度が上昇しなくなる光の強さのこと
**光補償点:光合成において、植物が出す酸素の量と吸収する二酸化炭素の量が同じ量になる光の強さのこと
各農作物における光飽和点と光補償点の目安
| 農作物 | 光飽和点(キロルクス) | 光補償点(キロルクス) |
|---|---|---|
| サトイモ | 80 | 4.0 |
| スイカ | 80 | 4.0 |
| トマト | 70 | 1.5 |
| キュウリ | 55 | 5.0 |
| メロン | 55 | 0.4 |
| ブドウ | 40-50 | 0.3-0.4 |
| サクランボ | 40-60 | 0.4 |
| ナス | 40 | 2.0 |
| ピーマン | 30 | 1.5 |
| イチゴ | 20-25 | 1.0-2.0 |
関連するコラムはこちら
低温・長雨が影響したトマトの日照不足
長雨や曇天続きの天候によって引き起こされる日照不足には低温を伴うことがあります。これらの条件には湿度の増加も加わってくるためトマトに対する悪条件(低温・日照不足・多湿)が益々増えてくることになってしまいますが、こうした悪条件は施設栽培であれば人為的に取り除くことが可能です。
たとえば低温対策は暖房を焚くことで解消します。冬期を通過する長期採りの作型では暖房が不可欠で、暖房期間中はトマトの生育適温にあわせて日中は23~28℃、夜間は4~13℃の間を目標に温度管理を行うと良いとされています。
日照不足は補光ライトを導入することで光合成を促すことができます。たとえば、ハウスが山、木、建物などの陰に立地している場合は生長点の上からライトを照射すると株全体に対して光を照射でき、日陰の時間帯の日照不足を補うことが期待できます。トマト群落内部での光合成をさらに効率的にしたい場合は、群落内に補光ライトを設置します。この方法はトマトの栽植密度が高い場合にも効果的で、群落内設置は天候不順および光合成効率改善と合わせて非常に合理的な方法として近年設置が進められています。
日照不足に起因した生理障害
ここまでトマト栽培と日照不足の関係について解説させていただきました。では実際に、日照不足になるとトマトにはどのような悪影響が現れるのでしょうか。それは「生理障害」として株や果実などに発現します。生理障害は不良な栽培環境で引き起こされて葉、花、果実などの生育に影響を及ぼす現象で、カビ、細菌、ウイルスによる病害とは異なります。
本章では、日照不足に起因した生理障害およびトマトに発生する代表的な生理障害を中心に解説したいと思います。
空洞果
夏や冬の高温期あるいは低温期に発生しやすく、日照不足も要因として指摘されています。トマトの栽培適期は気温の関係から春や秋とされていますが、周年栽培が可能になって夏や冬に栽培すると花粉の成熟や稔性に異常が生じるため花粉の代わりに着果ホルモンを使用します。ホルモン剤による受精は果実内に種子を作らないため、果実ゼリー部や果肉が発達せず空洞果が生じるとされています。
心腐れ果
心腐れ果は空洞果に発生しやすく、特異的に品種“桃太郎”に発生が多いとされています。果実に発生しますが、果実の外見からは本症状を判別しにくいとされ、商品価値は無く出荷先からのクレーム対象としても扱われるため厄介な生理障害といえます。土壌水分や高温によるストレスに起因する微量要素吸収阻害が原因といわれているようですが、根の極端な乾燥を避け、日照不足を改善して空洞果を抑制することが対策の一つとされています。
尻ぐされ病
尻腐れ病は「病」という文字が使われていますが病害ではなく生理障害に分けられています。トマトのカルシウム欠乏症が原因でミニトマトや中玉トマトでの発生は少なく、大玉トマトに発生しやすいです。商品価値は無く、食品加工に使用することも殆どありません。糖度を上げようとして極端な水切り栽培を行うと発生が助長されるので注意しましょう。
つるぼけ(花落ち)
つるぼけは定植前の土づくりにおいて、元肥で窒素を過剰に施用すると発生します。いわゆる窒素過多です。窒素過多は、多くの農作物において病害を助長する要因となっていますが、トマトの場合はつるぼけ(花落ち)も発生します。つるぼけは初心者にありがちなトマト栽培の失敗事例で、肥料が少ないから元気が無いと勘違いし、液肥などで少量ずつ追肥を行って更なる悪化を招くことが多いようです。品種にあった栽培方法をよく調べ、土づくりの際も肥料成分をしっかり確認するようにしましょう。
関連するコラムはこちら
トマトの日照不足の解消に最適な植物育成用LED
ハレルヤ
ハレルヤはトマトの生長点の上部や樹間に設置することで、日照不足を解消するLED照明です。トマト向けには円柱状の本体から二方向に照射できる両面発光タイプを樹間に設置すると群落内補光ができます。分電盤は不要で、コンセントがあれば直ぐに使うことができます。
日照不足を解消して生理障害に負けないトマト栽培を
天候をコントロールすることはできません。3か月予報などで天候の情報をキャッチしたとしても、実際にトマト栽培のシーズンにならないと細かい気象はわからないと思います。つまり、日照不足になってから日照不足対策をしてもすでに遅い場合があるといえます。今回は日照不足対策に対して補光用LEDライトに着目しましたが、葉面散布や土づくりでも日照不足による生育不良を多少なりともカバーすることができます。葉面散布であれば継続施用によって微量要素(ホウ素やモリブデンなど)などの養分補給によって生育を補助する効果が得られますが、土作りは定植後には行えないので、やはり日照不足とわかる前に実践しなければなりません。このような観点からいえば、トマトの日照不足対策は病害虫対策と同程度の重要度を見据えるべきかと思います。
今回のコラムが皆様のお役に立つならば幸いです。
こちらのコラムも是非ご覧ください!
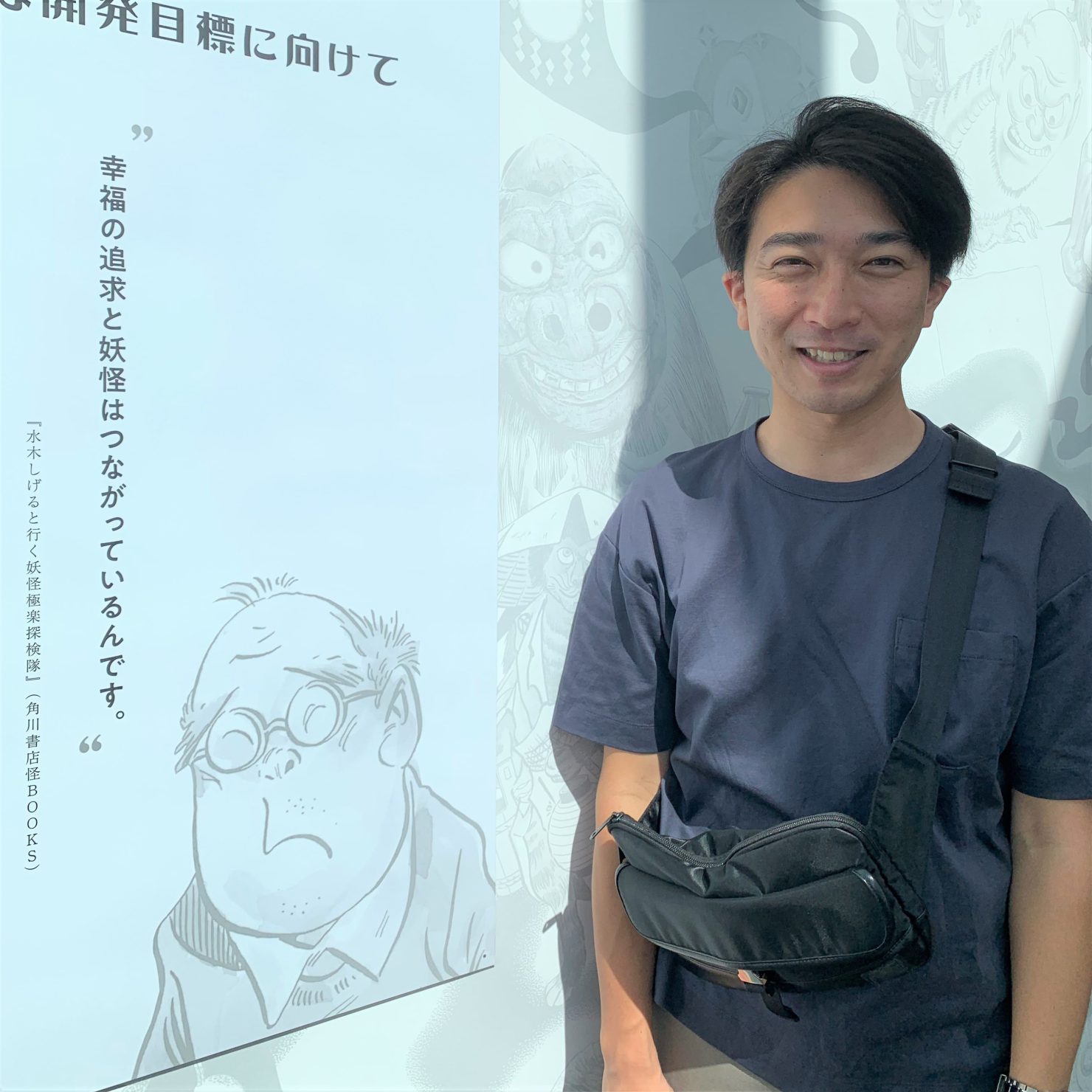
コラム著者
小島 英幹
2012年に日本大学大学院生物資源科学研究科修士課程を修了。その後2年間農家でイチゴ栽培を経験する。
2021年に民間企業数社を経てセイコーステラに入社。コラム執筆、HP作成、農家往訪など多岐に従事。
2016年から現在まで日本大学生物資源科学部の社会人研究員としても活動し、自然環境に配慮した農業の研究に取り組む。研究分野は電解機能水農法など。近年はアーバスキュラー菌根菌とバイオ炭を利用した野菜栽培の研究に着手。
検定、資格は土壌医検定2級、書道師範など。
-
日照不足を解消する補光用高性能LEDハレルヤ
- 高いPPFDで植物の補光を助ける
- 遠赤色LEDチップの搭載で光合成効率がさらにアップ!!
- 施設栽培では照射範囲が広い120cmタイプを推奨
- 自宅の観葉植物にはコンパクトな60cmタイプを推奨
-
高強度繊維の乱反射白色防草シートTheMORE
・三層構造の高強度繊維を採用
・表裏が白黒なので抜群の防草効果
・反射率88%以上(400-700nm)で果実色付けにも
・目安耐用年数7年 -
クエン酸、アミノ酸、微量要素を配合した琉球泡盛由来の液体肥料BioSもろみ
高温および低温ストレス緩和の泡盛由来液体肥料
【もろみM】アミノ酸・クエン酸・微量要素のオールラウンド肥料
【もろみKC】果実品質向上と光合成サポートに強み
【もろみJS】成り疲れ予防・回復の有機JAS肥料