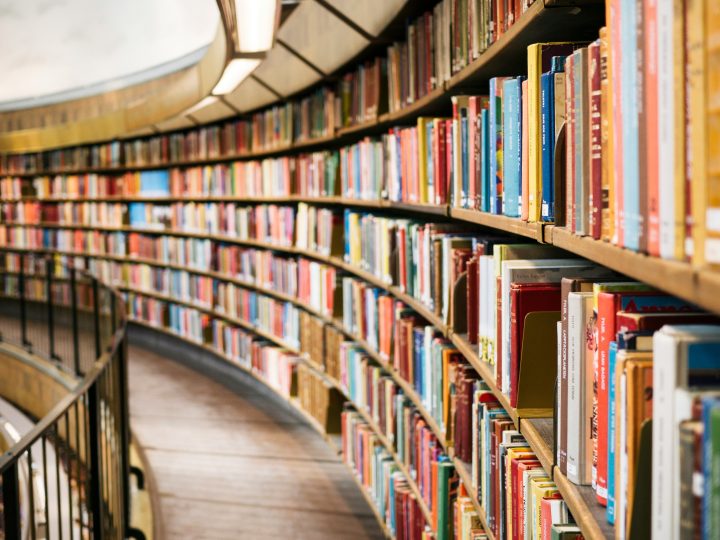灰色かび病とは?
灰色かび病は、糸状菌の一種であるボトリチス・シネレア(Botrytis cinerea)によって引き起こされる病害で、トマトをはじめ、イチゴ、ナス、キュウリ、花き類など多くの作物に被害をもたらします。カビの仲間であるこの菌は、高温多湿の環境を好むため、梅雨期や換気が不十分な施設栽培では特に発生リスクが高まります。
感染が始まると、葉や茎、果柄、果実などあらゆる部位に灰色がかった病斑やカビ状の菌糸が広がり、見た目を著しく損ねるだけでなく、果実の腐敗や落果、ひどい場合には株全体の枯死にもつながります。病原菌は非常に繁殖力が強く、胞子が風や雨、作業時の接触などによって容易に飛散し、健全な株へ次々と感染を拡大させます。剪定や収穫時の傷口、虫害や裂果などによる損傷部位から侵入しやすく、一度定着すると防除が難しいのが特徴です。
灰色かび病は、収量・品質の低下だけでなく、販売機会の損失や次作への感染源となることから、経済的にも大きなダメージを与える重要病害といえます。
灰色かび病が発生しやすい環境
高湿度や高温
灰色かび病は、高湿度と適度な気温がそろった環境で特に発生しやすい病気です。病原菌であるボトリチス菌は湿った空気を好み、高湿度になると胞子の発芽や菌糸の伸長が活発になります。日中に蒸し暑く、夜間に温度が下がりきらない状態が続くと、ハウス内に結露が生じ、植物体表面に水滴が長時間残るため、菌の繁殖に最適な条件が整います。
ボトリチス菌は、生育可能温度が約2〜31℃と幅広く、最も活動が活発になるのは23℃前後とされています。特に相対湿度が97%以上かつ気温が20〜25℃の環境下では、わずか1日で菌糸の伸長が始まり、2〜3日以内には分生子(新たな胞子)を形成することが確認されています。つまり、気温と湿度が上昇すると、短期間で感染サイクルが進行する極めて繁殖力の高い菌といえます。灰色かび病の胞子の発芽率は、相対湿度が90%を下回る環境で著しく低下することが確認されています。
トマト栽培において、このような条件が整いやすいのは、冬春作型では3月前後、夏秋作型では6〜7月または9月頃とされています。これらの時期は日中の温度上昇と夜間の湿度上昇が重なり、ハウス内で結露が発生しやすくなるため、菌の発芽や感染が助長されます。さらに、灰色かび病が厄介なのは、菌の繁殖期がトマトの収穫期と重なる点です。果実の成熟が進む時期に防除作業の時間を確保するのは難しく、薬剤散布の制限や作業負担の増大により、病気の拡大を抑えにくくなります。そのため、発生を未然に防ぐ環境管理や予防的対策が、最も重要な防除のポイントの一つとなります。
長雨や曇天
特に長雨や曇天が続く時期は、日射量の低下とともにハウス内の温度・湿度バランスが崩れやすくなります。換気が十分に行われない温室では湿気がこもり、空気の流れが停滞することで病原菌が活発に増殖しやすい環境が形成されます。
また、光量不足によって植物の蒸散作用が弱まり、葉から水分が放出されにくくなるため、内部の湿度はさらに上昇します。加えて、雨天時はハウスの開放時間が短くなりがちで、結果的に湿度の高い状態が長時間続くことになります。こうした状況は、灰色かび病菌の繁殖にとって理想的な条件となります。特に梅雨や秋雨の時期は、気温が20℃前後と菌の発育適温に近いため、発生リスクが一気に高まります。冷暖房を使用している施設栽培においても、夜間から早朝にかけての温度管理が不十分だと、ハウス内で結露が発生し、菌の増殖が助長されます。
関連コラム:トマト栽培における日照不足とその症状
栽培環境の過密化
トマトを過密に植えすぎると、株間の風通しが悪くなり、湿度が高くなるため、灰色かび病の病原菌にとって好都合な環境が生まれます。特にハウス栽培では、換気不足により湿度が高まり空気が滞留すると、蒸れによって葉面が常に湿った状態になり、胞子の発芽や菌糸の伸長が促進されます。
また、株が生長するにつれて葉や茎が重なり合い、日光が届きにくい陰の部分が増えることも問題です。光が当たらず風が抜けにくい部分では、水滴や結露が長時間残り, そこから病原菌が侵入して感染を広げるリスクが高まります。
このため、適切な株間の確保や不要な葉の除去、枝の剪定による通風の確保が、灰色かび病の発生を抑えるうえで欠かせません。病原菌が好む「高湿・停滞・陰」の状態をできるだけつくらないことが大切です。
枯死部や傷口
枯れた葉や落花した花弁、そして剪定や収穫作業で生じた傷口、害虫による食害痕などがあると、そこから灰色かび病の病原菌が侵入しやすくなります。これらの部位は植物体の組織が弱っているため、表皮が破れやすく、菌が付着するとすぐに菌糸を伸ばして内部に入り込みます。
特に、湿度が高い状態では傷口の乾燥が遅れ、感染リスクがさらに高まるため注意が必要です。古い下葉や枯れ葉、咲き終わった花弁をそのままにしておくと、そこが菌の繁殖源となり、周囲の健全な株にも感染が広がるおそれがあります。
トマトに見られる代表的な症状
灰色かび病は菌糸が広がると、植物のさまざまな組織を侵し、褐色から灰色の病斑を作り出します。葉、茎、花、実などどこにでも病状は表れます。
葉や茎の症状
灰色かび病の初期症状として最初に見られるのは、葉や茎に現れる小さな褐色〜灰色の斑点です。これらの斑点は水に濡れたように見える水浸状斑点を呈することもあり、拡大とともに周囲の組織を腐らせていきます。病気が進行すると、斑点の中心部に灰白色のカビ状の菌糸が現れ、やがて粉状の胞子が表面を覆うようになります。この段階になると病斑は急速に拡大し、葉柄や茎の組織が腐敗して養水分の通導が妨げられ、茎がしおれたように垂れ下がり、葉が縮れて部分的に枯死するといった症状が現れます。
果実の症状
果実に灰白色のカビが生え始めると、表面がまるで粉を吹いたような状態になります。これは病原菌の分生子が密生しているためです。未熟果では果実が水っぽく柔らかくなる「軟腐化」と呼ばれる状態に陥り、内部組織が崩壊してドロドロに腐敗することもあります。このように病斑やカビに覆われた果実は外観が著しく損なわれ、商品価値が一気に低下します。生食用や出荷用としての利用が難しくなるだけでなく、収穫物の廃棄率が上昇し、経済的損失も大きくなります。灰色カビ病が多発している施設では、まだ緑色の果実にも「ゴーストスポット」と呼ばれる白い円状の病斑が現れることがあります。
幼果では咲き終わった花弁に菌が発生し、そこから果実表面へと広がることがあります。感染した幼果は肥大が止まり、そのまま軟化・腐敗してしまうことも少なくありません。こうした果実上の病斑は、やがて周囲の健全な果実や株への新たな感染源となり、被害が連鎖的に拡大していきます。
うどんこ病との違い
うどんこ病も白い粉状のカビが植物体を覆う病気ですが、灰色かび病とは発生条件や症状の質感が異なります。うどんこ病はやや乾燥気味の環境でも発生しやすいのに対し、灰色かび病は高湿度が大きなトリガーとなります。両方とも菌が原因である点は共通していますが、見た目の色味や組織の腐敗度合いに差があるため、よく観察すると見分けがつくでしょう。「殺菌剤」は、どちらか一方にしか効かない場合が多く、誤った薬剤で対処すると効果が得られないことがあるので、病状を正しく判断することが大切です。もし判断が難しい場合は、地域の農協や専門家に相談するなど、病斑部を持参して診断を受けるのも手段の一つです。
トマト栽培における灰色かび病の予防策
換気・湿度管理の重要性
灰色かび病の最大の発生要因は高湿度です。病原菌のボトリチス菌は湿潤環境を好み、空気中の相対湿度が高い状態が続くと胞子が容易に発芽・増殖します。特に施設栽培では、朝夕の温度差によってハウス内の水分が凝結し、葉や茎、果実の表面に水滴が付着することで、病気の発生リスクが一気に高まります。そのため、換気や暖房を上手に活用して湿度をコントロールすることが重要です。雨の多い時期や梅雨明け直後は外気が多湿なため、どうしても湿気がこもりやすくなります。
「雨が降っているから」といって換気窓の開放を控えると、湿度が抜けず、逆に病気の発生を助長するおそれがあります。外気との温度差が大きくなる朝方は、早めの換気で内部の湿度を下げ、結露の発生を抑えることが効果的です。結露を防ぐことで、果実表面が長時間濡れた状態になるのを防ぎ、病原菌の発芽を抑制できます。定期的な換気、除湿、ハウス内の空気循環を意識的に行い、結露や滞留湿気を防ぐことが極めて重要です。
関連コラム:ビニールハウスの換気方法|作物に最適な環境を目指して
マルチング
土壌からの病原菌の跳ね上がりを防ぐためには、マルチングが非常に有効です。マルチングとは、ビニールや不織布、ワラなどで土の表面を覆う栽培方法で、雨水やかん水時の水はねを軽減し、土壌中に潜む灰色かび病菌や他の病原菌が果実や下葉に付着するのを防ぐ効果があります。さらに、マルチによって地表の水分蒸発を抑えることで、ハウス内の湿度上昇をある程度緩和できることもポイントです。これにより、葉面や果実の表面が長時間湿った状態になるのを防ぎ、病原菌の発芽・感染を抑制する効果が期待できます。マルチングは雑草の発生抑制や地温の安定化にもつながり、トマトの生育環境全体を改善する副次的効果もあります。
適切な株間の確保
株間を適切に確保することは、灰色かび病の予防において非常に重要です。株間を広く取ることで、ハウス内の風通しが良くなり、湿度を適切にコントロールしやすくなります。空気が循環し、葉や果実の表面に水滴が残りにくくなり、病原菌の発芽や感染を抑えることができます。過密な栽培は一見すると収量を増やせそうに見えますが、株同士が接触して蒸れやすくなり、灰色かび病など湿度を好む病気の発生リスクを高める要因になります。特に下葉や株元周辺では通風が悪化し、カビの繁殖や害虫の潜み場所にもなりかねません。
発病果や発病葉、花弁や古い葉の除去
灰色かび病は、発病果や発病葉、花弁などが強い伝染源となります。病斑が現れた葉や果実をそのままにしておくと、表面で形成された胞子が風や作業中の接触によって周囲の株へ飛散し、短期間で感染が拡大します。病斑を確認した部分は早めに除去することが極めて重要です。また、灰色かび病の菌は枯れた花弁や葉先などの弱った組織から侵入しやすいため、こうした部位をこまめに取り除くことも効果的です。特に花弁が果実表面に付着したまま放置されると、そこが感染の起点になることが多く注意が必要です。
また、病原菌は除去した残さや落ち葉の上でも生存し、越冬することができます。取り除いた病葉や果実を放置すると、次作の感染源となるおそれがあるため、必ず場外に持ち出して処分するか、適切に埋設・焼却処理するようにしましょう。
適切な農薬散布
予防散布が重要
灰色かび病の場合、胞子の発芽から感染までのスピードが速く、条件が整うと数日で病斑が広がることがあります。発病前の段階で予防散布を計画的に行い、病原菌の侵入や定着を未然に防ぐことが基本方針となります。発病が確認された場合は、被害を受けた果実や茎葉を早めに除去し、病原菌の拡散を防ぐとともに、発病初期の段階で適切な薬剤防除を徹底することが大切です。
薬剤の連用は避け、ローテーション散布を
同じ系統の薬剤を繰り返し使用すると、薬剤に対する耐性菌が出現するおそれがあります。これは、同一の作用機構を持つ薬剤を連続的に散布すると、病原菌の中からわずかに耐性を持った個体が生き残り、それが世代を重ねて増殖していくためです。結果として、これまで効果があった薬剤が効きにくくなる「薬剤耐性化」が進行する要因となります。
実際に、1970年代からトマトの灰色かび病防除に使用されてきたベンゾイミダゾール系の殺菌剤(例:ベノミルなど)や、ジカルボキシイミド系の殺菌剤に対しては、すでに日本各地で耐性菌の発生が確認されています。これらの耐性菌は防除効果を著しく低下させる要因となり、現場での対策を難しくしています。
このような問題を防ぐためには、複数の有効成分や作用機構を持つ薬剤を輪番(ローテーション)で使用することが重要です。異なる系統の薬剤を計画的に切り替えながら使用することで、耐性菌の出現を抑え、防除効果を長期間維持することができます。
生物農薬は単剤使用が基本
生物農薬は、微生物や天然由来の成分を活用して病害虫を抑制する防除資材であり、化学合成農薬に比べて環境負荷が少なく、残留リスクも低いことから注目を集めています。一方で、その成分は微生物の生存性や天然物質の安定性に大きく左右されるため、他の薬剤と混用すると有効成分が変質したり、微生物が死滅して効果が低下したりする場合があります。生物農薬は基本的に単剤で使用することが原則です。混用を検討する場合は、必ず製品ラベルやメーカーの混用適否情報を確認し、事前に小面積での試験や専門機関への相談を行うことが望まれます。
散布方法としては、暖房機の送風ダクトを利用して、生物農薬をハウス内全体に行き渡らせる方法があります。暖房機からの温風はハウス内を均一に循環するため、その風を活用して生物農薬の菌などの有用微生物を空間全体に飛散させることができます。
関連コラム:
・農薬散布の正しい方法と注意点|安全・安心な作物作りを目指して
・農薬が効かなくなる?害虫や病原菌の薬剤抵抗性について解説
曇天時は過度なかん水を避ける
晴れた日には光合成が活発に行われ、葉の気孔が大きく開きます。このとき葉の温度も上昇するため、植物体から水分が盛んに蒸発・放出され、蒸散量が増加します。蒸散は根からの吸水と連動しているため、晴天時にはそれに見合った十分なかん水が必要となります。一方で、曇天や雨天のように日射量が少ない日は、光合成の活動が鈍り、気孔の開きも小さくなるため、蒸散量は大きく低下します。その状態で晴天時と同じ量のかん水を行うと、過剰な水分が滞留し、湿度を上昇させる原因となります。
資材を消毒する
前作の圃場で発生した病原菌は、支柱や番線などの資材の表面に付着し、次の作にも感染を広げるおそれがあります。トマト灰色かび病では、そのような二次感染の事例が報告されています。灰色かび病菌は低温でも長く生き残る性質があるため、栽培終了後に資材の消毒を徹底して感染の連鎖を断つことが重要です。支柱などの資材には、次亜塩素酸カルシウム製剤やベンチアゾール乳剤を使って殺菌できますが、番線やハウスフィルムなどへの効果的な処理方法にはまだ課題があり、新しい殺菌技術の実用化が期待されています。
トマトの灰色かび病対策におすすめの換気扇|空動扇&空動扇SOLAR
トマト栽培において灰色かび病は、最も注意すべき湿度由来の病害のひとつです。曇天や夜間にハウス内の湿度が高まり、葉や花弁が濡れた状態が長く続くと、灰色かび病菌の胞子が発芽し、感染が広がります。特にハウス上部の温度差によって生じる結露水滴は、病原菌の繁殖を助長する原因となります。こうした環境を改善するために開発されたのが、空動扇および空動扇SOLARです。
空動扇は、風や太陽の力を利用してハウス上部の湿気や熱気を効率的に外部へ排出する換気扇です。風力でベンチレーターが回転し、天長部から熱だまりを排出します。太陽光を利用する空動扇SOLARでは、自然風がないときでもソーラーモーターによってファンが駆動し、安定した排気を維持できます。これにより、日中の高温多湿状態を防ぐだけでなく、夜間の湿度上昇や結露発生も抑え、病害の原因となる過湿環境の改善に貢献します。
また、空動扇には形状記憶スプリングによる温度自動開閉機構が備わっており、設定温度(0〜40℃)に応じて換気弁が自動的に開閉します。これにより、負担となる換気作業を軽減しつつ、ハウス内の環境を適切に保つ効果が期待できます。電源配線が不要で、既存のパイプハウスにも簡単に後付けできます。
資材の消毒におすすめ|オゾン散水器
次亜塩素酸カルシウムやベンチアゾールなどの薬剤は、金属やプラスチック表面に対して化学的に不安定な場合があります。たとえば、金属(番線)では腐食や変色の原因になったり、ビニール(フィルム)では劣化を起こったり、といった問題です。また、ハウス全体や長い番線を対象に薬剤消毒を行うのは、時間と手間が非常にかかるうえ、大量の薬液が必要になります。作業後の廃液処理も環境負荷や法的規制の観点から課題となっています。
オゾン散水器はボタン一つで瞬時にオゾン水を生成し、酸化作用によって細菌・真菌・ウイルスを短時間で不活化します。灰色かび病菌に対しても不活化が確認されており、 化学薬剤のような耐性菌の発達リスクが低いのも利点です。オゾンは分解後に酸素(O₂)へ戻るため、残留毒性がなく安全性が高いです。そのため、ハウス内資材やフィルム・金属部材への使用も比較的安全で、環境負荷が低い点でも優れています。
栽培中のトマトに農薬的な効果を期待してオゾン水を利用することは、農薬取締法に抵触してしまうため実施することができません
灰色かび病対策は「早期発見」と「予防」が鍵
灰色かび病はトマト栽培でよく見られる厄介な病気の一つです。発生後の防除は難しいため、早期発見と予防対策が何より重要です。普段からのこまめな観察と環境管理が、病気のリスクを減らし、良質なトマトを収穫するための第一歩となります。こまめなメンテナンスと正しい知識をもって、健康で美味しいトマトをたくさん収穫していきましょう。
関連コラム:
・トマト栽培における病害虫の種類と対策を解説
・トマト疫病の基礎知識まとめ|発生時の対策と予防(防除)策とは?
参考資料:
・果菜類における農薬耐性菌問題と防除対策(岐阜県農業技術センター)
・県内で発生している薬剤耐性トマト灰色かび病菌に対する有効薬剤の選抜(岡山県)

コラム著者
セイコーステラ 代表取締役 武藤 俊平
株式会社セイコーステラ 代表取締役。農家さんのお困りごとに関するコラムを定期的に配信しています。取り上げて欲しいテーマやトピックがありましたら、お知らせください。