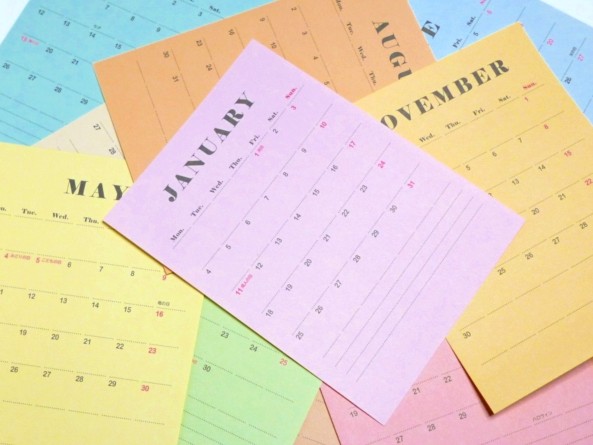ハウスによるアスパラガス栽培のメリット
アスパラガスは露地でも収穫は可能ですが、天候に左右されて品質がばらつきがでたり、病害の発生リスクが高まったりする場合があります。ハウス栽培(施設栽培)の最大の特徴は、気候や天候の影響を最小限に抑えられる点です。外的環境の影響が少なくなるため、露地栽培と比べて安定した品質と、計画的な出荷や収穫期間の延長による増収を実現できると考えられています。ハウス栽培は適切な栽培環境を保つことで、計画的な出荷が可能になります。近年では水田からの転作作物としても注目を集めています。
降雨による病害リスクを最小限に抑える
ハウス栽培では、降雨の影響を受けにくくなるという点がメリットの一つです。例えば、アスパラガスの主要な病気である茎枯病は、雨による泥はねなどで感染が拡大します。最も有効な対策は雨よけとされており、ハウス栽培では病害を引き起こす菌の発生や拡散を抑制しやすくなります。
収穫時期の調整で収益アップにつながる
ハウス内の環境を適切に管理することで、地域や季節の影響を受けずに生育を調整でき、収穫時期のコントロールが容易になります。外気温が低い時期でも、ハウス内の保温を適切に行えば早期にアスパラガスが成長し、市場が手薄な時期に高値で出荷が可能です。需要が高いときに集中して収穫を行えるため、利益率の上昇も期待できます。
収穫期間を長期化して単収を大幅に増やす
ハウス栽培では、アスパラガスの収穫期を長く維持することができます。露地栽培に比べて収穫期間を数週間以上も延ばせる場合があり、これが積み重なると単位面積あたりの収量が飛躍的にアップします。長期収穫による安定的な出荷は、アスパラガスをブランド化する際の強みにもなります。
アスパラガスのハウス栽培スタート前に抑えておくポイント
ハウス栽培の作型
「春どりのみ」「春どり夏秋どりを行う2季どり」「春どりから休まずに夏秋どりをおこなう長期どり」の3つに加えて、露地で 1~2 年かけて育てたアスパラガスの根株を掘り上げ、ハウス内の温床に伏せ込んで加温し、冬のあいだに若茎を収穫する「伏せ込み促成栽培」という栽培方法があります。気温や降水量、日照など、その土地の環境条件に合った作型を選ぶことで、安定した生育と収量が期待できます。
アスパラガスの品種選び
アスパラガスの主な種類には、グリーンアスパラガス・ホワイトアスパラガス・ロングアスパラガス・ムラサキアスパラガス・ミニアスパラガス・アスパラソバージュなどがありますが、日本で生食用として最も流通量が多いのはグリーンアスパラガスです。主要産地で作付けされている主な品種を示した表がありましたので抜粋します。苗の品質の安定性や栽培マニュアルが豊富などを考えると「広く市場に流通している主力品種」を選ぶ方が安全で有利です。ただし、差別化を図りたい場合には、あえて希少品種を選ぶという選択肢もあります。
| 都道府県名 | 主な品種 |
|---|---|
| 北海道 | ガインリム・スーパーウェルカム・ウェルカム・ゼンユウガリバー |
| 佐賀県 | ウェルカム |
| 熊本県 | ウェルカム・スーパーウェルカム |
| 長崎県 | ウェルカム |
| 福岡県 | ウェルカム・スーパーウェルカム |
育苗で押さえておくポイント
アスパラガスのハウス栽培でとても重要なのは強い苗を育てることです。育苗段階でしっかりと水分と栄養を与え、軽量で根張りの良い苗に仕立てると、定植後の生育がスムーズに進みます。
アスパラガスの種は吸水促進が大切でから、播種前に種をすり鉢などでこすって表面に傷をつけて、25~28℃程度の水に3日間程度浸すことと発芽率を高められると考えられています。育苗時には温度管理や光量の確保も重要で、適度な日当たりと保温を両立させることが丈夫な苗のもとになります。地温は20℃が理想的(最低地温は15℃)で、地温が足りない場合は、培地を加温する電熱線ヒーターなどで温める必要があります。成長を揃えるために地温にムラがないようにするのもポイントです。発芽温度は28~30℃ですが、発芽確認後は温度を徐々に下げます。アスパラガスの育苗期間は100日以上と長く、温度管理も手間がかかりますので、苗を購入するというのも選択肢の一つです。
定植前に必要な土壌づくり
アスパラガスは深根性の植物です。根の80%は土の深さ40cmの場所に分布しているため、深層まで通気性と排水性の良い土壌を好み、腐植物質の多い砂壌土~埴壌土が適しているといわれています。多年生で一つの株で10年以上も収穫ができるため、定植前に堆肥や有機質肥料を加えたり、深く耕したりするなどの土壌改良が欠かせません。水はけが悪いと根腐れの原因になるため、畝を高くするなどの工夫も必要です。郡山市の栽培マニュアルに掲載されていた土壌改良に関する目標について示された表や土づくりの方法に関する手順がありましたので以下に掲載いたします。
土壌改良の目標(アスパラガス栽培マニュアル(郡山市)より抜粋)
| 項目 | 目標 |
|---|---|
| 有効土の深さ | 40cm以上 |
| 地下水位 | 50cm以下 |
| pH | 5.5~6.5 |
| EC | 0.2~0.6mS/cm |
土づくりの方法(アスパラガス栽培マニュアル(郡山市)より抜粋)
- 緑肥の導入(定植前年の夏)
セスバニアなど、直根性で岩盤を粉砕するものが良い。 - 土壌診断の実施
改良の目標は上記の表のとおり。 - 硬盤層の粉砕の実施(プラソイラ、サブソイラなど)
- 完熟牛ふん堆肥の投入
10aあたり20t以上を投入する。 - プラウなどによる深耕の実施
また同マニュアルによれば、桑園の跡地は、共通の土壌病害である紫紋羽病が発症するリスクが高いため、避けたほうが良いと紹介されています。リンゴやブドウなどの果樹やサツマイモの跡地も発症の危険性が高いのかもしれません。
アスパラガスの定植後の管理のポイント
定植後の初年度は株をしっかり養成し、それ以降は安定的な収穫を目指します。アスパラガス栽培で大切なのは、若い株を無理に収穫しすぎず、十分に生育させることです。特に定植1年目は葉や茎の光合成能力を最大限に活かし、地下部に栄養を蓄積させる時期です。翌年以降の収量や品質を左右するため、この段階での管理に力を入れることが長期間の安定生産にも直結します。
定植1年目の管理と注意点
定植1年目は養成期と位置づけ、アスパラガスの立茎を十分に確保することが重要です。無理に収穫すると株が弱り、翌年以降の生産量が落ちる可能性があります。また、肥料を過剰に与えると茎が過剰成長し倒伏のリスクも高まるため、バランスの良い追肥が望ましいです。
定植2年目以降の収穫ピークと株の維持
定植2年目からは本格的な収穫期を迎えますが、株の健康を最優先に考えましょう。施肥と灌水のタイミングを調整し、ハウス内の温度管理を適切に行うことで収穫を長期間継続できます。収穫量ばかりに注目せず、株自体のバランスを崩さないことが、翌年度以降の持続的な収量アップにつながります。
アスパラガスの病害や害虫|特徴と対策
アスパラガスは高温多湿の環境下で斑点病や褐斑病、茎枯病などの病害が発生しやすく、湿度が高い季節や気温差が大きいときに注意が必要です。一般に定期的な薬剤散布を行い、ハウス内の換気を十分に行うことで菌を繁殖させにくい環境を作れると考えられています。
また、害虫による被害も大きく、早めに農薬散布を行い被害拡大を食い止める必要があります。アスパラガスの葉や茎を好むジュウシホシクビナガハムシやアザミウマ類など、見つけにくい小型の害虫も多いため、日常的な点検が重要です。食害が拡大すると収量だけでなく品質にも影響が出ます。
主要病害の特徴と対策
斑点病
擬葉や側校に数mm程の小さい斑点を多数形成し、黄化・落葉などを引き起こす病気です。多発すると翌年の収量低下の要因となります。 茎葉間の通風の悪い場合や高湿度条件で発生が助長されるため、換気を十分に行うことが大切です。斑点病は、発病初期に薬剤散布を行っても被害の拡大を抑えきれない事例もみられるため、収穫期間中は予防的な薬剤散布が必要です。夏の高温で停滞し、秋雨の時期に拡大しやすい病気だとされています。
褐斑病
斑点病と似ており病斑の表面に肉眼で確認できる灰色~黒色の分生子塊を形成する病気です。高温で湿度が高まり、株が茂りすぎて風通しが悪くなると発生しやすくなります。発生のピークは、梅雨期から秋にかけての蒸し暑い時期です。感染から発病までの潜伏期間が20~30日と長いため、肉眼で確認できる病斑を確認した時には感染が進んでしまっている可能性が高いです。発病前からの予防的な薬剤散布が重要で、不要な茎葉は整理し過繁茂を避けて通風を確保することが大切です。
茎枯病
カビの仲間で、茎に赤褐色紡錘形の病斑を作り、株を枯らす病気です。病原菌は雨などの跳ね上げにより若茎に感染するため、梅雨や秋雨の時期に増える傾向があります。発病の初期段階では、効果の高い薬剤を用いて早めに対処します。また、雨よけ施設やマルチを利用して泥はねを抑えることで、感染拡大を防ぐ効果も期待できます。圃場内の病茎や残渣を処分し伝染源をなくすことも大切です。特に病原菌は病斑内で越冬するため、伝染源が残っていると翌年の伝染源となるため必ず片付けます。
株腐病
フザリウム属菌が原因となる典型的な土壌病害 です。発生しやすいのは 定植後2〜3年程度の若い株 で、茎葉が黄化し、地下茎やりん芽が腐敗します。りん芽が傷むことで、枯れた茎は簡単に抜けてしまうのが特徴です。主な対策としては、排水性を高めたり高うねにするなど、土壌環境を改善すること、また 発病初期に登録農薬を散布すること が挙げられます。さらに、連作を避けることも有効な予防策になります。
立枯病
株腐病と同じくフザリウム属菌が原因で、現れる症状もよく似ているため、外見だけでの判別は困難です。本病は収穫期の若茎に発生するタイプと、株自体に発生して立ち枯れを起こすタイプがあります。若茎では茎の褐変や亀裂が主な症状として見られます。一方、株に発生した場合は、地際部にピンク色のカビが生じ、さらに進行すると地下茎や根の維管束が褐変し、最終的には根腐れを引き起こします。一般に対策は株腐病と同じだとされています。(関連コラム:アスパラガスの茎枯病に有効な対策とは?防除のポイントと対処方法)
疫病
フィトフトラ属菌が原因となる土壌病害で、比較的近年になって発生が確認された病気です。主に地際から数十センチ程度までの低い位置に、水浸状の病斑が現れるのが特徴で、その後は病斑が灰白色に乾燥し、周囲が赤褐色に変化していきます。若茎に発生した場合は、穂先が曲がるなどの萎凋症状が見られます。病気が進行すると萌芽が止まり、鱗芽・地下茎・貯蔵根にまで腐敗が拡大します。特に土壌の排水不良が疫病の発生を助長することが明らかになっています。発生を防ぐためには 圃場の排水性を確保することが重要です。
紫紋羽病
感染してから実際に症状が現れるまでに数年を要することが多い病害で、特に桑園の跡地や長期間の連作圃場で発生しやすい傾向があります。初期には生育が悪くなり、葉が早い段階で黄化し、草勢が徐々に弱って最終的には枯死します。また、地下茎や根は腐敗して内部が空洞化します。一度発生してしまうと、現状では決定的な防除方法がないのが実情です。
主要害虫の特徴と対策
ジュウシホシクビナガハムシ
ハムシ科クビホソハムシ亜科に属する体長約6mmの害虫で、成虫は背面に赤褐色で黒斑をもつのが特徴です。年に1回発生し、3月頃からふ化した幼虫は新芽を食害、土中で蛹化し6月頃から成虫が発生します。成虫が新芽の先端部を中心に食害すると、新芽が曲がるため品質が低下(商品価値を失う)します。収穫期に成虫の餌となる「取り残し茎」を少なくし、地上に出ている茎をなるべく短くするといった対策を行います。また、収穫期以降に農薬散布を行うことで次世代の幼虫の密度低下をはかるといった作業が大切です。
アザミウマ類
アスパラガス栽培で問題となるアザミウマはネギアザミウマが多いようです。ネギアザミウマは収穫物である若茎を加害して品質低下を招くためやっかいな害虫です。6月頃~9月頃までに被害が集中します。防虫ネットを張ってハウス内への侵入を防止し、防除効果の高い農薬を散布することが大切です。最近ではスワルスキーカブリダニ、ククメリスカブリダニといった天敵昆虫を併用する事例も増えてきています。(関連コラム:アスパラガスをネギアザミウマから守るには?)
ハウス内の病害虫対策のポイント
ハウスという密閉空間だからこそ、病害虫対策の徹底が不可欠です。ハウス内は外部からの侵入が少ない反面、一度発生した病害虫が急速に蔓延しやすい環境でもあります。そのため、こまめな点検と早期駆除、環境管理が重要です。密閉空間をうまく活かして安全な農薬や天敵昆虫を導入すれば、効率的かつ環境負荷を抑えた防除が可能になります。
被害株の早期除去や環境管理
ハウス内で病害虫を発見した場合、まず被害株や被害部位を早急に除去することが蔓延防止の近道となります。さらに、適切な温度と湿度を維持して、通気を確保することで病害虫が繁殖しにくい環境を作り出すことが大切です。こうしたこまやかな管理が品質保持と長期収量確保の要になります。
適切なタイミングでの農薬散布や天敵の利用
予防的な薬剤散布を行ったり、病害虫の発生早期に農薬を散布するほうが、大量発生してから焦って対策するよりも効果的です。近年では、天敵昆虫を導入して化学農薬使用を抑える事例も増えています。状況に応じて農薬散布や天敵利用を選択し、安定的な防除を実現しましょう。
関連コラム:アスパラガスの害虫対策|効果のある資材をご紹介
1年目と2年目以降の栽培のポイント(例:ウェルカム)
多収性で生育の揃いが良いウェルカムという品種で、1年目の栽培と2年目以降の栽培内容について解説します。
1年目(株を育てる年)
ビニールハウスで育てる際、一般に1年目は収穫はせずに株を大きくすることが目標となります。春に苗を植えたら、いくつも芽が出てきますが、太くて元気な芽を6〜8本だけ残して立茎します。残した親茎は株の栄養を作る大事な部分です。残りの芽は摘み取ります。ハウス内は風通しが悪いと湿気がたまりやすく、病気の原因になります。葉が重なりすぎないように、ひもで軽く束ねたり、支柱で誘引して風が通るようにします。水やりは土がベタベタにならないように注意します。ビニールハウスは雨が入らないため、乾きすぎは良くありませんが、過湿にすると根腐れの原因になります。秋になると葉が黄色くなり、冬には完全に枯れます。枯れた葉は刈り取り、ハウスを整理して、冬の間に株を休ませます。
2年目以降(収穫できる年)
2年目からいよいよアスパラを収穫できます。ビニールハウスでは、温度管理ができるので、2〜3月から春芽の早出しの収穫が可能です。春芽は20〜25cmくらいの長さで切り取り、毎日または隔日で収穫します。春の収穫は、年間収量の半分以上を占める重要な時期です。収穫後は、株が疲れないよう肥料は控えめにし、水やりや換気で環境を整えます。春芽の収穫が終わったら、親茎を育てるために8〜12本だけ立茎します。親茎は夏の光合成で栄養を作り、翌年のアスパラを太くする重要な役割があります。夏はハウス内が高温になりやすく、アスパラが疲れやすい時期です。無理に収穫せず、ハウスの換気や葉の整枝をしっかり行って株を健康に保ちます。病気が出やすい時期なので、湿度管理も大切です。秋になると、再び太い秋芽が出てきます。秋芽を収穫したら、冬に向けて株を休ませます。葉が黄色くなったら刈り取り、ハウス内を整理して冬の管理に備えます。
スマート農業の活用で作業効率・品質を高める
センサーやICT技術を導入することで、省力化と高品質生産を両立させる道が開かれます。近年、ハウス栽培では温度や湿度、土壌水分を自動制御するシステムの導入が進んでいます。コンピューターやセンサーを活用するスマート農業により、作業時間を大幅に削減すると同時に、アスパラガスの最適な生育環境を常に保つことが可能です。データの蓄積によって栽培ノウハウが可視化されるため、生産者同士の情報共有や品質向上につながっています。
ビニールハウスの温湿度対策に最適な換気扇|空動扇/空動扇SOLAR
アスパラガスの生育適温は20℃程度のため、ハウス内の高温状態が続くと、光合成速度が低下することで同化養分不足に陥り、擬葉が枯死、奇形芽の発生、タケノコ茎・裂開の発生することで収量低下を招きます。またハウス内の高湿状態が続くと斑点病、褐斑病、茎枯病といった病害が発生しやすくなるため注意が必要です。そこでご紹介したい資材がビニールハウス専用の換気扇空動扇/空動扇SOLARです。10坪~15坪あたりに1台を設置することで、ビニールハウスの上部に溜まった熱だまりや湿度を排出し、アスパラガスの生長に適した環境に整え、病害虫対策に効果を発揮します。湿度を抜けるため作業者の労働環境を快適に整えてくれることもメリットです。電気を使わないためとってもエコな換気扇です。
まとめ・総括
ハウス栽培アスパラガスの安定生産には確かな準備と定期的な管理が欠かせません。ハウス栽培によるアスパラガス生産は、天候に左右されにくく、収穫期間の延長や作業効率の向上といった数多くのメリットがあります。一方で、ハウス内は密閉空間であるため、病害虫が発生すると急速に被害が拡大するリスクも存在します。適切な設備投資と日頃の管理、そしてスマート農業の活用を組み合わせることで、収量と品質を両立させながら一年を通じた安定出荷が実現しやすくなります。
関連コラム:
・アスパラ栽培の基礎知識と育て方
参考資料:
・アスパラガス、冬の手入れをぬかりなく|JAいがふるさと
・アスパラガスの栽培方法・育て方|タキイネット通販
・アスパラガス(ハウス) 技術体系|熊本県野菜振興協会
・アスパラガス 現在の気候変動影響と適応策|栃木県
・アスパラガス斑点病に対する各種殺菌剤の効果|北日本病虫研報
・アスパラガス褐斑病の防除対策の徹底について|佐賀県
・アスパラガス茎枯病徹底防除の“処方”|長野県アスパラガス生産振興プロジェクト
・各地で話題の病害虫|植物防疫病害虫情報 第19号

コラム著者
満岡 雄
玉川大学農学部を卒業。セイコーエコロジアの技術営業として活動中。全国の生産者の皆様から日々勉強させていただき農作業に役立つ資材&情報&コラムを発信しています。XとInstagramで最新情報を投稿していますのでぜひ御覧ください。
◆X
https://twitter.com/SEIKO_ECOLOGIA
◆Instagram
https://www.instagram.com/seiko_ecologia