この文章の一部でも読者の参考になれば幸いです。
日本のバナナ栽培地域について

弊社にもまだまだ少数であるがバナナを栽培されている方からのお問い合わせをいただく。本来バナナは月の平均気温27℃が栽培適温で熱帯性の気候に適しており、温暖性の気候である本州での栽培は難しいとされてきた。そのため日本ではこれまで小笠原諸島や南西諸島などでしかバナナは栽培できなかった。ところが最近は東海や関東、東北でもバナナが栽培されている。そして結構お高い。1本あたり1000円前後。1000円あればスーパーマーケットのフィリピンバナナが30本位買えそうな価格で庶民の私には手が出せない。ネットで調べると無農薬栽培されていて皮まで食べられるというバナナが多く、1本1000円はこれに対する付加価値も含まれているのであろう。
私が初めて国産高級バナナを認識したのは5、6年前だったと思うが宮崎ブーゲンビリア空港のお土産コーナーで見掛けた。1本800円位だったと記憶しているが、当時マンゴーで発生する炭疽病と軸腐病、イチゴのうどんこ病や灰色かび病などに関する仕事で頻繁に宮崎県に訪れており北は都農町、南は日南市、都城市や西都市などにも訪れたが目立ったバナナの栽培圃場は見かけなかった。同じくマンゴーの病害、チャの炭疽病や輪斑病に関する仕事で度々訪れた鹿児島県の、特に霧島市から佐多岬の大隅半島もやはりバナナ圃場の記憶はなく、道の駅や直売所ではマンゴー、ビワ、桜島小みかんの果実がたくさん売られていた。
ところが沖縄県に訪れると一変、公園や道路の脇にもバナナが植わっている。沖縄県のバナナは「島バナナ」と呼ばれることもあるが、沖縄県で栽培されている全てのバナナが島バナナではないことが勉強するうちにわかってきた。順を追って筆者の謎解きを論じていきたい。
こちらのコラムも是非ご覧ください
>>>マンゴー栽培で発生する病気|発生の仕組みと防除対策をご紹介
>>>イチゴの育苗方法について-育苗の手順、育苗の種類や苗の増やし
島バナナとは①|島バナナとの出会い

20代後半の頃、沖縄県に訪れた際にタクシーを半日チャーターして運転手のおじぃに南部を案内してもらったことがある。どこにあったのか、後部座席に座っていると「これでも食べな」とバナナを一房。多分10本位あったと思う。そのバナナがとても小さく、しかも真っ黒。腐ってきたから助けてほしいとおやつをお裾分けしてくれたのかと思った。食べてみると甘味でねっとりして絶品だった。これが島バナナとは露知らず、後になってわかったことだが筆者と島バナナの最初の出会いであった。最近は、沖縄県に行くと糸満市や名護市のファーマーズマーケットに行くことがあるので小さなバナナを見掛ければ買って食べている。関東のスーパーマーケットで売っているフィリピンバナナと比べても小さいのにとても高い。この島バナナ、今度は仕事で関わろうとは考えもしなかった。
因みに、タクシーのおじぃに案内してもらった中本鮮魚てんぷら店のもずく天ぷらはとても美味しい思い出だ。
こちらのコラムも是非ご覧ください
>>>沖縄の農業と農産物|熱帯気候で活躍する農業資材を紹介!
島バナナとは②|島バナナの歴史
いきなり話が反れてしまったが、島バナナとはなんだろうか。
ネットで調べてみると島バナナと呼ばれているバナナはどうやら「キングバナナ」という種類らしい。明治時代に小笠原諸島から沖縄県に持ち込まれたようだ。ではキングバナナは小笠原諸島に自生していたものなのだろうか。そうではないようで、江戸時代後期の1800年代前半にハワイから持ち込まれたと推定されている。ハワイから小笠原諸島、小笠原諸島から沖縄県とスケールの大きな話で、調べてみてやっとわかったことだ。つまり、沖縄県における島バナナ(キングバナナ)の歴史は150年間ほどということ。しかし実際に沖縄県のファーマーズマーケットで島バナナとして売られているものは形状も大きさも一様ではない気がする。
沖縄県のバナナの謎

この1時間後、写真を送ってくれた彼女からLINEが入った。この写真をお母さんに見せたところ島バナナではない可能性があるとのことで、沖縄県で栽培されたバナナは島バナナと呼ばれていると考えていたところに衝撃的な一報だった。写真を送った当人も沖縄のバナナは全て島バナナと思っていたようだ。もう一度写真をよく見ると、果実のサイズが長く大きく見える。どうやらフィリピンバナナのように果実サイズが大きいバナナは島バナナとは呼ばないようで、なるほど、沖縄県には島バナナのように果実サイズが短く小さいバナナと島バナナとは呼ばれない果実が長く大きいバナナが栽培されていることがわかった。
島バナナとは一体何なのか…
アップルバナナ

商品ラベルにアップルバナナと印字されている。島バナナと印字されているバナナも一緒に写っていた。因みに写真は2023年4月に撮られたものだ。最近めでたく6回目のトゥシビーを迎えたお母さんが島バナナとそうでないバナナを誤認するとは考えにくい。前述の通り、果実サイズが小さいバナナが島バナナと認識されていることは間違いなさそうだが、島バナナと呼ばれているバナナには複数の種類があることがわかってきた。つまり、150年前にキングバナナが小笠原諸島から沖縄県に持ち込まれて以降、キングバナナ以外の果実の小さなバナナが沖縄県に入っている。昔の大航海と違って現代は輸送手段が多様になり苗の持ち込みも難しくないので、よくよく考えれば色々な種類があっても不思議な話ではない。
銀バナナ

「バナナ ギン」と書いてある。第三の島バナナ発見か…。ネットで調べてみると銀バナナというものが沖縄県の北部や南部で栽培されていることがわかった。あるサイトによると銀バナナはナムワ系のバナナでタイ王国が主な産地らしい。
これではっきりしてきたが、最初に沖縄県に持ち込まれた島バナナはキングバナナであったけれども、150年の時を経て色々な種類の小さなバナナが沖縄県に流入し、沖縄県民に島バナナと認識されるようになってきたと推定できた。
筆者的島バナナの結論

ファーマーズマーケットいとまん うまんちゅ市場
この写真は2022年9月に筆者が糸満市のファーマーズマーケットで撮った写真だ。バナナコーナーは広めのスペースが確保されていて黄色に熟れてきたもの、緑色でまだ硬いものが一緒に売られていた。特に黄色のバナナは名護市のファーマーズマーケットで売られていた島バナナと比較してもずんぐりむっくりした印象である。筆者は写真手前の4本1パックの商品を購入してオキコのゼブラパンのお供に頂いた。
那覇市第一牧志公設市場

YouTubeや書籍を調べてみると…

YouTube
YouTubeでは「農の共有」というチャンネルを参考にした。沖縄県のコーヒー、アボカド、バナナ、マンゴーなどの果樹をはじめ沖縄県の農業について農場を訪問した内容を動画に纏めており非常に有意義なチャンネルだ。2023年度、本レポートの筆者が通っている日本大学でコーヒー栽培に関わることになりコーヒーについて調べるうちに辿り着いたのが「農の共有」である。このチャンネルには沖縄県のバナナについても取り上げられており、すべてを視聴できていないが(5/1現在、1221本の動画がアップされている)いくつかの動画を観るとかなりたくさんの種類のバナナが沖縄県で栽培されていることがわかる。また、聴いていると出演者は島バナナと他の種類のバナナを区別して発言していると感じた。更に、ファーマーズマーケットでバナナを購入するときに種類を特定して購入できない(種類が何か示されないで売られている)ケースもあるような内容もあった。因みに、動画で取り上げられていたバナナの種類の一部はマイソールバナナ、ベジタブルバナナ、ボリビアバナナ、合掌バナナである。
書籍
書籍では「バナナの足、世界を駆ける」を参考にした。北海学園大学の先生がアフリカや東南アジアのバナナをアカデミックに解説しており非常に参考になる。本書の一部に沖縄県の島バナナに関する記述があり先生の体験をもとにした内容であるが、島バナナについて「不思議な存在」と冒頭に綴られていることは本レポートの筆者も共感できた。この書籍でもYouTube同様、島バナナと他の種類のバナナが区別して執筆されている。また、色々な種類のバナナが県内に拡散していることも調査されている。
島バナナへのアプローチ方法と視点
筆者が学習、調査した内容から導いた結論はまったく的外れであるとは思っていないが、YouTubeや書籍も参考にすると、沖縄県のバナナへのアプローチの仕方が島バナナの理解を異にすると考えてみた。筆者は現地で売られていた小さなバナナと沖縄県にいる友人らの認識、つまり消費者視点からアプローチした。YouTubeは農家をはじめとする栽培者視点から、書籍はデータに基づいて書かれており比較的に研究者視点でアプローチされている。島バナナはキングバナナであるだろうことも判っているし、キングバナナ以外のバナナが沖縄県にたくさんあることも間違いない。島バナナという呼称が沖縄県の人たちにどう認識されているのか、筆者はもう少し消費者目線を持って学習、調査をしてみようと思う。
沖縄県のバナナ出荷量の謎

沖縄県農林水産部から農林関係統計(令和4年3月)が発行されており、この中では令和元年度産のバナナの出荷量と結果樹面積が市町村別に記載されている。バナナに関するこの統計の留意すべきことは、「バナナ」の統計内容であり島バナナと限定していないことである。
何もない場所からバナナが出荷されている…?
少し見れば誰もがこの統計のおかしなことに気付くと思うが、結果樹面積が0haにも関わらず北部では5.5t、中部では14.9tの収穫量をあげている。この統計によると北部の収穫量5.5tは全て恩納村から得られていることになっているが、ここまでにしばしば登場している名護市のファーマーズマーケットのバナナのパッケージには名護市や今帰仁村が産地として記載されている。つまり、行政が把握していないバナナがそれなりに流通していることがわかる。北部の収穫量5.5tは正確な収穫量よりもかなり少ない数字である可能性が高く、結果樹面積を全く把握できていないことから鑑みてもどれ程の差異が存在するのか判断も難しいのが沖縄県のバナナ事情だ。
沖縄県ではバナナを自家用で食べるために自宅の庭に植えて栽培することがある。個人宅の庭で立派に育ったバナナの樹は実際に見てきたし、バナナに限らずパパイヤやマンゴーが植わっているケースも珍しくない。庭でなくとも趣味で畑をやっている人がそこでバナナを育てていることも当然あるだろう。本州でもカンキツ、カキやブドウなど庭や畑に植えられていることが珍しくないがこれと何ら変わらない。筆者が考えたのは、沖縄県の場合はこの自家用バナナが売りに出されており、これならば行政が結果樹面積を把握することを困難する要因になり得ることである。ただしこの考察も限定的数量の範囲で、北部や中部の合計20t近くのバナナに対して自家用バナナの量は氷山の一角よりも小さいと想像できる。大量のバナナは一体どこで栽培されているのか謎である。
バナナ栽培に役立ちそうなセイコーステラの商品
ほんの少数ではあるがバナナを栽培されている方からお問い合わせをいただいている。その中から実際に購入していただいた商品をピックアップしてPRさせていただきたい。補足だが、いずれの商品も本州のお客様である。
スマートキャッチャーⅡ

空動扇/空動扇SOLAR

終わりに

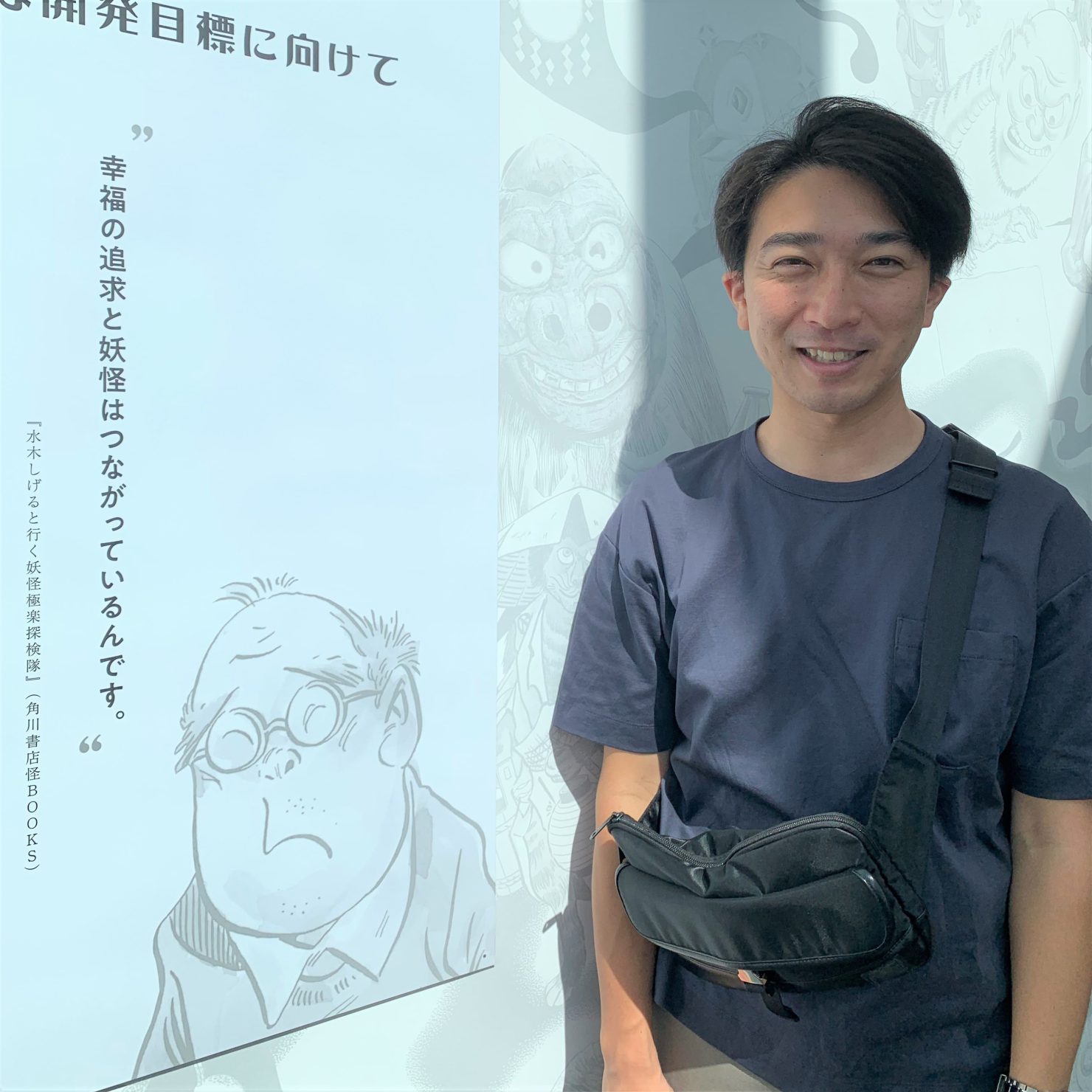
コラム著者
小島 英幹
2012年に日本大学大学院生物資源科学研究科修士課程を修了。その後2年間農家でイチゴ栽培を経験する。
2021年に民間企業数社を経てセイコーステラに入社。コラム執筆、HP作成、農家往訪など多岐に従事。
2016年から現在まで日本大学生物資源科学部の社会人研究員としても活動し、自然環境に配慮した農業の研究に取り組む。研究分野は電解機能水農法など。近年はアーバスキュラー菌根菌とバイオ炭を利用した野菜栽培の研究に着手。
検定、資格は土壌医検定2級、書道師範など。






